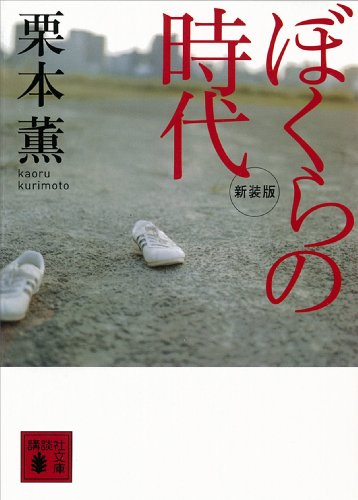まず、一部を伏字にして引用。
●●●●は厄介な存在である。議論の通俗さや粗雑さや幼稚さを批判しても、通俗であり粗雑であり幼稚であるのが「一般民衆」の意見であると居直られてしまう。精緻な議論や抽象的な論理を提示したら、「ゾウゲの塔」に閉じこもっている高踏的な「知識人」だと、逆になじられることになる。
さて、●●●●とは誰でしょう? 今の時代のいろんな名前が思い浮かぶはず。先の引用は、山本幸正『松本清張が「砂の器」を書くまで ベストセラーと新聞小説の一九五〇年代』から。でも、●●●●は松本清張ではない。
●●●●は、同書の全三部のうち第一部を使って論じられた石川達三。清張論なのに別の作家に三分の一も使うの、と最初は思った。だが、新聞小説というマスの読者を相手にした人気作家がいかに権威と傲慢を有するようになったかの考察は興味深い。後のテレビ文化人、SNS文化人にも通じるところがある。
また、石川達三が批判した谷崎潤一郎『鍵』と川崎長太郎の私小説の共通性に関する指摘にも感心した。互いに読まれることを前提にして書かれた夫婦の日記という形式をとった前者は疑似書簡体小説であり、読者は盗み読むように読むことになる。また、川崎は当時プチブームの有名人であり、メディアを通して読者に私生活を覗き見られていた。そうした現実と虚構の浸潤を石川が「不潔」と感じたのではないかとする著者の推理には引きこまれる。
『松本清張が「砂の器」を書くまで』は、1950年代の新聞小説という当時最大級の大衆的媒体における人気作家の系譜として石川達三-松本清張に着目し、マジョリティ代表としてふるまう石川的な立場との相似&相違から清張を位置づけようとする。この論点の設定は面白い(2作家の比較考察を後半でもっと語ってほしかったといううらみはあるが)。
清張が地方紙に自身が小説を連載していたことを題材に使った「地方紙を買う女」に触れたうえで、やはり新聞連載小説だった『砂の器』において、同じ紙面にそれまで載っていた現実の前衛芸術の記事をパロディにしたような文章を作中に織りこんだことをたどる。どのようなメディア環境で自作を発表しているのかを意識していた清張の創作姿勢が、著者の読み解きによって浮かび上がっていく。
さらに『砂の器』ではミュージック・コンクレートの実践者である音楽家・和賀英良より、探偵役となる今西栄太郎のほうが方言を手がかりとし、それこそ小耳にはさんだことから推理を進めるなど「耳」を使っているという指摘は卓見。